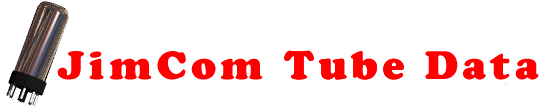

<12AT7/A>
High-Frequency Twin Triode 双3極管
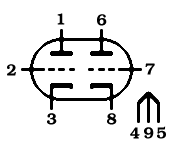
9Pin M T
1 - P2 2 - G2 3 - K2 4 - H 5 - H 6 - P1 7 - G1 8 - K1 9 - HT

12AT7のIM特性
1000Hz と 1200HzのAF オシレータを用意し,-6dBコンバイナーで混合して12AT7 に与えています. 12AT7 の動作条件は Rp=270k,Rk=3.9k,Ebb=100V の真空管ハンドブックの標準動作で,利得は 28.9 倍,8.4V 出力で歪率が 4.5% とデータブックに記載されています.(プレート電圧は約37V.) 出力は141T に8556A のプラグインユニットで BW=30Hz で観測しています. このスペアナ出力をA/D 変換してMac に送り,観測データをエクセルで処理しました. 特に入力をレベルを -10dBV x2 とした方は入力信号以外のありとあらゆる周波数に「お化け」が 出ていて驚きます.-14dBV x2 の方は,主要な2次,3次の歪成分がグループごとにまとまっていて 分かりやすいです. *** 各周波周成分 (dBV) *** 入力レベル -10dBV -12dBV -14dBV 基本波 f1 (1000 Hz) 18.1 16.4 14.4 f2 (1200 Hz) 18.2 16.3 14.4 2次高調波 2*f1 (2000 Hz) -11.6 -13.7 -17.3 2*f2 (2400 Hz) -11.4 -14.0 -17.1 2次相互変調積 f2-f1 ( 200 Hz) -4.8 -7.8 -10.9 f1+f2 (2200 Hz) -4.7 -7.8 -10.9 3次高調波 3*f1 (3000 Hz) -28.1 -50.2 -51.2 3*f2 (3600 Hz) -26.4 -39.8 -41.4 3次相互変調積 2*f1-f2 (800 Hz) -27.1 -43.9 -39.8 2*f2-f1 (1400 Hz) -27.4 -43.5 -39.6 2*f1+f2 (3200 Hz) -27.5 -42.7 -39.7 2*f2+f1 (3400 Hz) -27.6 -43.1 -39.6 高調波と相互変調積の関係がほぼ,理論的な予測に合っているのが分かります. 3次高調波の片側が 40dBV 以下にならないのは,使ったオシレータのうち1200Hz の方の歪率がひどく悪いことが原因です. 測定中,スペアナを間違って 12AT7 のグリッド,つまり入力に接続して測定したのですが,なんと グリッド側ですでにかなりの相互変調歪が観測できます.測定系は 600 Ohm になっていて,比較的 低いドライブインピーダンスで駆動されているに関わらずです. 12AT7 のヒータを切りカソードが冷えると歪は完全に消失しますから,信号源に歪が含まれている わけではありません.追実験が必要のようです. -10dBV = 0.316V で 利得が約30 倍で,2信号の合成で,PEP レベルが2倍になっていますので完全に クリップが始まっています.-14dBV が実用的な限界です. 12AT7 IM特性 (25KByte)
12AT7の初速度電流
この実験は 1)初速度電流の電流−電圧特性,球によるばらつき 2)初速度電流とグリッドで発生する2次歪の関係,理論的な予測との比較 を手元でできる範囲で調査してみました. 1)初速度電流の電流−電圧特性,球によるばらつき 対象にした球は12AT7 で,その 1-3 pin の No.2ユニットを測定しています. プレート電圧も測定の重要な条件ですが,今回はプレート負荷 270k Ohm,供給電圧 100V (安定化)としてプレート電圧そのものは成り行きにまかせてあります. 手持ちの 12AT7,新旧あわせて 10本以上測定してみましたが球によって初速度電流が 1000 倍 ぐらい違います. グラフに取り上げた3つのサンプルは以下のとおりです.#1 のみ新品,あとは中古ですが, いずれの球も真空管試験器の相互コンダクタンステストでは良品と判定されるものです. #1 6201 (Westinghouse) #2 USN-12AT7WB 6201 (General Electric) #3 12AT7WB (SYLVANIA) #1 が測定した中では初速度電流が平均的なもの,#2,#3 がそれぞれ例外的に小さいもの,大きいものです. グラフをご覧いただければ,「グリッド電圧 0.3V で初速度電流は10倍の変化する」という近似が さほど間違っていないことがわかっていただけると思います.私の測定系では 0.05uA 以下の測定が 困難で,グラフが暴れますが,0.05uAから 3uA の範囲で,片対数のグラフでほとんど直線になります. 歪測定をする動作点(Ec=-0.9V)における初速度電流は #1 0.055 uA #2 0.0041 uA #3 3.4 uA となります.(#2 については外挿) 2)初速度電流とグリッドで発生する2次歪の関係,理論的な予測との比較 歪の測定は,低周波帯のスペアナを使い,高調波歪を測定しています. この実験では測定の簡単な高調波歪を測定しています.測定は駆動インピーダンス Rg を変えながら 0.2Vrms(-14dBV)の信号を 12AT7 のグリッド゛に与え,そのグリッドの信号をスペアナに入力して 周波数成分の分析をします.プレートからの出力を観測しているわけではなく,あくまでも グリッドでの信号を観測します.球のヒータを切ってカソードが完全に冷えた時に観測される, 測定系の残留歪みは2次歪 -80dB(0.01%) 以下,3次歪み -74dB (0.02%) となります. #1 のサンプルについて,ヒータ OFF,Rg = 1k Ohm,10k Ohm について測定した例を先の初速度電流の グラフの下に添付していますのでご覧ください. 歪測定の結果をまとめると以下のようになります.( -: 測定限界以下) *** Harmonic Distortion Contents *** Rg = 100 Ohm 1k Ohm 10k Ohm #1 2nd. - 0.044 % 0.38 % (0.055uA @Ec = -0.9V) 3rd. - 0.023 % 0.15 % 4th. - - 0.047 % #2 2nd. - - 0.035 % (0.0041uA @Ec = -0.9V) 3rd. - - 0.019 % 4th. - - - #3 2nd. 0.31 % 2.2 % 9.9 % (3.4uA @Ec = -0.9V) 3rd. 0.11 % 0.80 % 1.0 % 4th. 0.028 % 0.13 % 0.30 % 5th. - 0.014 % 0.20 % 初速度電流,駆動インピーダンスが大きくなるにしたがって歪が増加すること,特に2次歪に 注目すると,初速度電流,駆動インピーダンスにほぼ比例していることがわかります. 12AT7 初速度電流特性 (15KByte) このページの実験データは,林 輝彦氏よりご提供いただきました.
連絡先: jimcom123@hotmail.com JimCom
COPYRIGHT 1996,97 JimCom このサイト内の画像・図面等の情報を無断で使用する事を禁じます.
このページの実験データは,林 輝彦氏よりご提供いただきました.
連絡先: jimcom123@hotmail.com JimCom
COPYRIGHT 1996,97 JimCom このサイト内の画像・図面等の情報を無断で使用する事を禁じます.